ここから本文です。
ページ番号:26840
掲載日:2025年6月1日
教員免許申請は原則として、電子申請・届出サービスで御申請ください。
(電子申請・届出サービスを利用する場合も、入力後申請書類の送付は必要です。)
※電子申請・届出サービスによる申請では、当課に書類到着後、申請完了までに数日~1週間程度かかることがあります。
直近で当該免許状を使用した任用を予定している場合は、任用先とよく御相談いただき、速やかにお手続をお願いします。
チェックリストを必ず御確認いただき、不備のないよう御申請ください。
申請書類に不備があった場合、メール等にて不備書類の追加提出等を御連絡します。
不備がなくなった時点で手数料を納付いただき、納付後に申請書控えをアップロードします。
控えの到達をもって申請完了となります。
申請方法
原則として、電子申請・届出サービスで御申請ください。
電子申請・届出サービスによる申請(電子申請)
手数料をペイジー(Pay-easy)を用いて対応のATM(現金可)やインターネットバンキングで納付したり、クレジットカード又はコード決済を用いて納付したりすることができます。
「教育職員免許状授与願(様式第1)」及び「履歴書(様式第2)」はオンラインで入力し、送信後、印刷・署名します。
(申請内容の印刷方法等は送信完了画面及び同時に送信されるメールで御案内します。)
上記書類と添付書類を郵送等により提出してください。
※添付書類は「申請に必要な書類」を御確認ください。
電子申請を始める際は、下記の「教員免許申請フォーム」ボタンからアクセスしてください。
手続の流れについては教員免許電子申請の手続(PDF:863KB)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
「利用者登録」はしなくても申し込めますが、複数件の申請を行う場合は利用者登録をしてから申請すると便利です。
電子申請や電子納付のQ&Aは、教員免許に関するQ&Aを御覧ください。
来庁による申請
今回申請する免許状による任用開始が迫っており、電子申請だと手続が間に合わない等、来庁して申請しなければならないやむを得ない事情がある場合は、ページ下部の「お問い合わせフォーム」から御連絡の上、申請書類を揃えて持参してください。
来庁の場合の受付時間は教員免許トップページを御確認ください。
※来庁して申請した場合でも、申請受理から免許状発行までにかかる時間は電子申請と変わりません(申請から免許状発送までの期間参照)。
※令和5年10月2日から、窓口で申請する場合の教員免許手数料について、キャッシュレス決済を開始しました。
詳細及び使用可能ブランドは出納総務課ホームページ(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
申請に必要な書類
※下記「注意事項」欄に有効期限の記載がない書類は、発行日を問いません。
有効期限を設けているものは、当課に全ての必要書類が不備なく提出された時点で有効期限内である必要があります。
※申請書類記載事項の偽りやその他不正の手段により免許を取得した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
|
必要書類 |
注意事項 |
|---|---|
|
|
|
1 教育職員免許状授与願(様式第1) 【署名をした原本】 |
|
|
2 履歴書(様式第2) 【署名をした原本】 |
|
|
3 卒業(修了)証明書【原本】 ※学位記や卒業証書は不可 |
|
|
4 「学力に関する証明書」【原本】 ※成績証明書や修得単位一覧は不可 |
|
|
5 教員免許状の写し |
|
|
6 過去に更新・延期・免除・回復手続をしたことがある場合のみ、その証明書の写し |
|
|
9 戸籍抄本(又は謄本)【原本】 |
|
|
10 返信用封筒(免許状用) ※「レターパックプラス (600円・赤)」又は 「角2封筒+切手530円」 ※宛名・送付先を記入 ※角2封筒で同時に5種類以上の免許状を申請する場合、620円分の切手が必要です。 |
|
|
〇手数料について ※手数料は、当課で書類の不備等がないことを確認後にお支払いいただきます。 |
|
※複数の免許状を同時に申請する場合は、下記を御覧ください。
Q&A:複数の免許状を申請したいのですが、申請書類は1部でよいですか?
※学力に関する証明書の取得について
1. 2つ以上の大学等で、申請する教員免許用の単位を修得した場合
→それぞれの大学等から「学力に関する証明書」を受けてください。
例:A大学を、養護教諭用の単位を一部修得して卒業し、B大学で残りの単位を修得
A大学及びB大学、双方から養護教諭用の「学力に関する証明書」が必要
2. 卒業大学等で既に他の教員免許状を取得し、一部の単位を流用している場合
→取得済みの教員免許用の「学力に関する証明書」が併せて必要です。
例:A大学を卒業して小学校1種免許状を取得し、単位を流用してB大学で養護教諭用の単位を修得
- A大学からは、小学校教諭1種用の「学力に関する証明書」が必要
- B大学からは、養護教諭用の「学力に関する証明書」が必要
3. 卒業大学等で文部科学省令に定める科目(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器各2単位)のみ修得し、別の大学で残りの単位を全て修得した場合
→上記の4科目各2単位について、併せて証明が必要です。
例:A大学を上記の科目のみ修得して卒業し、B大学で養護教諭の免許に係る単位を全て修得
- A大学から、学力に関する証明書ないし基礎科目の証明書が必要
- B大学から、養護教諭用の学力に関する証明書
※適用法令(「新法」「旧法」など)について
新法:教員免許を取得できる大学等に平成31年4月1日以降に在籍を開始し、必要単位などの取得条件を揃えた場合
旧法:教員免許を取得できる大学等に平成31年3月31日以前から在籍しており、その在籍期間中に必要な単位などの取得条件を揃えた場合
平成31年3月31日以前から在籍していたA大学の在籍中にB大学の在籍を開始した場合
- B大学の在籍開始が平成31年3月31日以前の場合
A大学またはB大学の在籍が途切れる前に必要単位などの取得条件を揃えた場合は、「旧法」が適用になります。 - B大学の在籍開始が平成31年4月1日以降の場合
A大学の在籍が途切れる前に必要単位などの取得条件を揃えた場合は、「旧法」が適用になります。
B大学に引き続き在籍中であっても、A大学の在籍が途切れた時点で必要単位などの取得条件を揃えることができなかった場合は、「新法」が適用になります。
平成31年3月31日以前から在籍していたA大学を卒業後、平成31年4月1日以降にB大学に在籍を開始した場合
- 「新法」が適用になります。
「学力に関する証明書」は、新法又は旧法に全て合わせてください。
例:A大学の在籍が旧法の時期であっても、B大学の在籍開始時期から新法が適用となる場合は、A大学B大学ともに新法の「学力に関する証明書」を取得してください。
再授与申請や平成12年3月31日以前に大学等へ在籍開始した場合は、「旧法」よりも古い法令が適用になることがあります。
複数の大学等で単位を修得していた場合は、お問合せください。
申請から免許状発送までの期間
免許状は、申請されても即日発行はできません。
教員免許の申請から実際の発送まで、下記の授与等予定年月日(免許状に記載される発行日の予定日)から約1~2か月かかります。
なお、下記の「受付月日」は、当課で書類の不備等がないことを確認後、手数料納付が完了した日を指します。
|
申請書類の受付月日 |
授与等予定年月日 |
|
|---|---|---|
|
4月から2月 |
1日から14日受付 |
受付月の15日 |
|
15日から月末受付 |
受付月の翌月1日 |
|
|
3月 |
1日~14日受付 |
3月15日 |
|
15日~31日受付 |
3月31日 |
|
※土・日・祝日等は書類の受付・確認はできません。
なお、平日に当課で書類の不備等がないことを確認し、手数料納付依頼のメール送信後、手数料の納付のみ(電子納付に限る)は土・日・祝日等でも可能です(ただし、システムメンテナンス時等は納付できない場合があります)。
※授与等予定年月日から免許状の発送までの間に、公的な証明書は発行していません。


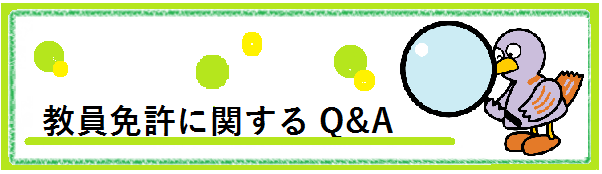
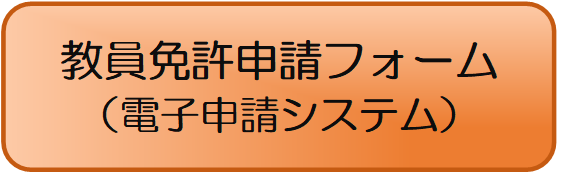 (別ウィンドウで開きます)
(別ウィンドウで開きます)