ページ番号:271076
掲載日:2025年12月3日
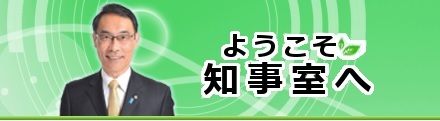
ここから本文です。
どこでも知事室(令和7年度)
令和7年度の実績は次のとおりです。
第1回
日時
令和7年7月1日(火曜日)10時00分~11時30分
場所
さいたま水族館 レクチャールーム(羽生市三田ケ谷751-1 羽生水郷公園内)
参加者
ムジナモ保全に取り組む羽生市ムジナモ保存会、学識経験者の方々(7名)
テーマ
テーマ「ムジナモ保全に関する現状と課題」~ネイチャーポジティブの実現に向けて~
参加者からの意見等
- 羽生市ムジナモ保存会は、昭和58年10月に発足し、現在会員数は法人・団体を含めて約130名である。ムジナモ栽培法の指導や自生地の紹介などの啓もう活動、生育に支障となる外来生物などの駆除などに加え、会員が自宅でムジナモを栽培したりしている。宝蔵寺沼ムジナモ自生地の環境を次の世代に残していきたいとの思いで活動を続けている。
- 埼玉大学及びムジナモ自生地研究チーム(埼玉大学以外の研究者)は、ムジナモ自生地の環境調査に加え、ムジナモの生命現象からムジナモと多様な生物がバランスよく生息できる環境創出を研究している。
- 羽生市教育委員会は、ムジナモの生育に支障となる天敵などの削減、草刈りなどの湿地環境の維持、水路の再生などに取り組んでいる。
- ムジナモを増やすためには、実はムジナモだけでなく、そこに住む動植物の環境ごと守っていくことが大切である。
- 自生地周辺の小学校の統廃合があったが、地元小学校児童へのムジナモ栽培の指導については、引き続き実施したい。
- さらに、地元小学校だけではなく県内の中学校や高校とも連携して、生徒の課題研究の場として使ってもらいたい。
知事から一言
- ムジナモさらには様々な生物の多様性というものを大切に育み、次の世代に私たちが持っている自然、そして多様性というものを残していくということが県の一つの役割であると考えている。
- ムジナモを広く知ってもらい、ネイチャーボジティブの意識を広めるためにも、人に来てもらって観光などの側面で地域の活性化を図っていくことも重要である。


第2回
日時
令和7年8月28日(木曜日)9時10分~10時40分
場所
農業技術研究センター久喜試験場 研修室(久喜市六万部91)
参加者
県内でトマト、きゅうり、いちご栽培に取り組む生産者の方々(6名)
テーマ
「埼玉県における施設野菜の現状と課題」~高温対策とスマート農業技術について~
参加者からの意見等
- 技術革新により、施設環境をモニタリングできる機器や、複数の環境データを統合的に分析して施設環境を自動制御できる装置が施設園芸に導入されるようになった。
- 炭酸ガス施用装置や細霧冷房装置とあわせて用い、植物の生育環境の最適化を通じて収量・品質が向上したり、農作業の軽労化につながるなどの成果が出ている。
- 設備投資をし、収穫量を増やしたいが、栽培環境が厳しくなっている中で、更なる人材確保の観点から、なかなか人を集めるのが厳しい現状がある。
- 新規就農だと最初から雇用は難しいので農福連携を始めた。地域で障害者の方々を雇用することで、やりがいを感じていただきながら働いてもらっている。農福連携をすることで、メリハリをつけた働き方改革も実践できている。
- 空きハウス情報を一括で集められる仕組みがあったら良いと思う。
知事から一言
- 県では「次世代施設園芸埼玉拠点」を整備し、スマート農業技術の収量増加・品質向上効果の実証を行うとともに、得られた成果をもとに、スマート農業技術の生産現場への導入を支援している。
- 本日の意見交換では、県内でトマト、きゅうり、いちご栽培を手掛ける生産者の方々から、高温対策でのご苦心や、スマート農業技術などを活用した取組のほか、経営や農福連携についてお話を伺い、多くの学びを得ることができた。今後の施策に生かしていきたい。



第3回
日時
令和7年10月30日(木曜日)9時30分~11時00分
場所
社会医療法人入間川病院 附属棟2階大ホール
参加者
病院の医療従事者をはじめ事務部門の方々(6名)
テーマ
「看護人材確保の現状と課題」~医療現場における看護業務改善の取組~
参加者からの意見等
- 看護業務の煩雑化や多様化、さらに看護師不足を背景として、看護業務の改善が求められる中、コロナ禍での業務負担軽減を目的にICT機器(AmiVoice)を導入していたが、業務改善の効果が今一つ見られない状況が続いていた。
- ICT機器を使用しない看護業務が多かったことに加え、ICT機器使用に対する規定作成や指導が不足していたことが課題であった。
- そこで、令和6年度、県の「ICT導入による看護業務改善を目指す病院へのアドバイザー派遣事業」にモデル施設として参加した。
- 派遣されたアドバイザーの助言に基づき、AmiVoice使用のマニュアルや基準の作成、使用タイミングの統一化に取り組んだ。
- これらの取組により、看護記録時間の削減や業務負担が軽減されたので、大変大きな成果があった。
知事から一言
- 県では、看護業務の効率化・省力化のためにICT機器やロボットの導入を目指す病院をモデル施設として選定し、アドバイザーを派遣することで、ICT機器導入等による看護業務効率化を実現できるよう支援している。
- 本日の意見交換では、看護師や事務部門の方々から、医療現場における看護業務改善の取組について様々なお話を伺い、多くの学びを得ることができた。今後の施策に生かしていきたい。

