ページ番号:2930
掲載日:2025年12月17日
ここから本文です。
腸管出血性大腸菌感染症流行情報
感染症発生動向調査では、2025年第50週(12月8日~12月14日)はO157 2例、O untypable(不明含む)3例の届出がありました。
腸管出血性大腸菌感染症では、下痢、血便、腹痛、発熱等の症状に続き、患者の6~7%に、発病後数日から2週間後に溶血性尿毒症症候群(HUS)などの重症合併症を発症することがあります。特に、お子さんや高齢者など抵抗力の弱い方は注意が必要です。
埼玉県の腸管出血性大腸菌感染症の発生状況
届出された症例を診断された週別に集計しました。
2025年第1週~
2025年第1週以降に診断された腸管出血性大腸菌感染症は、O157が64例、O26が30例、O103が15例、O111が4例、O8が3例、O115が3例、O159が3例、O91が2例、O28acが1例、O55が1例、O74が1例、O98が1例、O124が1例、O126が1例、O145が1例、O146が1例、O148が1例、O152が1例、O165が1例、O untypable(不明含む)が36例の計171例です。
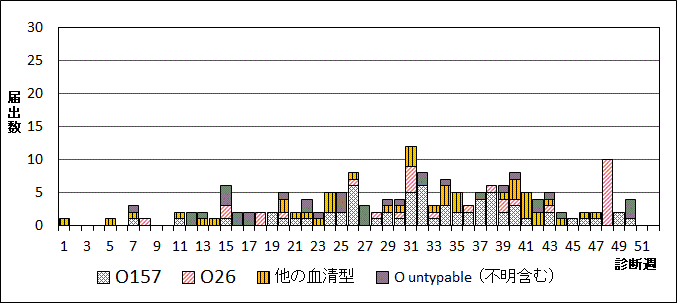
2024年第1週~52週
2024年第1週以降に診断された腸管出血性大腸菌感染症は、O157が98例(O157・O untypable同時検出1例含む)、O26が14例、O103が8例、O111が6例、O115が6例、O128が5例、O8が4例(O8・O25同時検出1例含む)、O91が4例、O55が3例、O76が1例、O121が1例、O145が1例、O168が1例、O178が1例、O181が1例、O untypable(不明含む)が29例の計183例です。

埼玉県の腸管出血性大腸菌感染症の原因究明調査
埼玉県では、腸管出血性大腸菌感染症の患者が発生した場合には、その原因を見つけ出して、感染の拡大を防止するための調査を行っています。調査は、県内共通の調査票(PDF:124KB)で行う疫学調査と患者から分離された菌を用いた細菌学的な調査です。
調査へのご協力とご理解をよろしくお願いいたします。
調査票はこちら→腸管出血性大腸菌感染症発生原因調査票(PDF:124KB)
O157等感染症を予防するには
(1)石けんと流水でよく手を洗いましょう。
- 特に、調理前、生肉を触った後、生で食べる食品を触る前など、調理の種類が変わるごとに手を洗いましょう。
- トイレ後の手洗いも十分にしましょう。
(2)よく加熱し、調理後は早めに食べるようにしましょう。
- 調理の際は、食品を中心部まで加熱しましょう(大腸菌は、75℃で1分間以上加熱することで死滅します)。
- 調理後はできるだけ早く食べ切りましょう。
(3)調理器具と食品の保管場所に注意し、清潔の保持を心がけましょう。
- まな板・包丁などは、肉用・魚用・野菜用など、使用目的別に使い分けましょう。
- 調理器具使用後は、洗剤でよく洗い、乾燥させた後、保管しましょう。
- 冷蔵庫や冷凍庫は食品別に袋分けするなど区分けし、こまめに掃除しましょう。
なお、腸管出血性大腸菌感染症の予防については、埼玉県庁のホームページをご覧ください。
週対応表
週に対応した月日を記載した表です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください