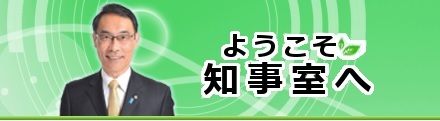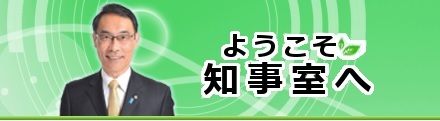創立109年の防災事業のパイオニアである同社は、火災発生時の異常熱や煙、赤外線などを検知するセンシング技術を強みとしています。
研究開発センターの先進技術部門では、この技術を応用し、橋りょうの劣化診断技術の実用化を進めています。
同技術は専用装置(加速度センサ)を橋りょうに設置し、振動や傾きを分析することで構造物の健全性を評価します。 これにより、目視では確認できない劣化や損傷の診断が可能です。
知事は専用装置の体験や施設見学を行い、代表者や社員と意見交換を行いました。

振動や傾きなどを分析する加速度センサの説明を受ける
知事
この技術について大変興味を持っています。例えば車両で巡回しながら測定を行い、設計値との差を確認することが可能でしょうか。
中野先進技術研究室主査
本技術は開発中ですので、現時点では1日程度のデータ収集を実施しております。将来的に、より短時間で簡便な計測ができるよう、技術開発に取り組んでおります。
知事
実は、私が最も関心を持っているのは下水管の点検です。例えば、加速度センサを使って振動の変化を検知することで、下水管の損傷箇所を特定することは可能でしょうか。
山岸センター長
非常に難しい問題だと考えています。橋りょうは長く細い形状のため振動しやすい特性がありますが、下水管は土で覆われ振動しにくい構造です。このため、下水管の損傷測定は橋りょうよりも難しい課題です。橋りょうの劣化診断技術をそのまま下水管の点検に応用するのは困難ですが、大学と連携して技術検討に取り掛かります。
知事
国土交通省の技術研究所や大学の方々に御協力いただきながら議論を進めておりますが、現時点では有効な解決策を見い出すには至っておりません。下水管の点検は日本全体にとって重要な課題ですので、今後も教えてください。
山岸センター長
日本全国には約74万の橋が存在しますが、今後20年ほどで、その半数以上が健全度の限界に近づくと予想されています。全ての橋を架け替えることは現実的に難しいため、延命措置を講じつつ、使用頻度の高い橋を優先して維持管理を行う必要があります。このような課題に対して、私たちは本技術が非常に有効であると考えています。
知事
まちづくりの観点から、我々は三郷市長の協力も得て、埼玉版スーパー・シティプロジェクトを推進しています。現在のインフラをそのまま維持することは困難ですので、物理的な面とまちづくりの両面から取り組まなければ、数十年後には大きな課題が生じると考えています。
ページの先頭へ戻る
まきの菜園&M's CURRY など
三郷市は、東京都に隣接する立地条件を生かし、都市型農業が盛んです。市の積極的な支援の下、アスパラガスやメロン、枝豆といった特産品の開発やブランド化に取り組み、高い人気を集めています。また、農業に加工や販売を取り入れて新たな価値を創出する、6次産業化に挑戦する農業者も多く見られます。
当日は、情熱あふれる4人の農業者が、それぞれ特色ある事例を紹介しました。
(1)自家製野菜を使った、幅広い層に人気のネパールカレー
(2)明治大学と連携した新農法で栽培されたアスパラガス
(3)SDGsの観点から規格外フルーツを活用したドライフルーツ
(4)有機農法で栽培したこだわりの小松菜を使用したふりかけ
知事は、農業者が東京都内などで移動販売に使用しているキッチンカーや、カレー専門店に併設された直売所を視察しました。また、ネパールカレーや自家製イチゴのスムージーを試食し、農業者4人との意見交換を行いました。

カレー専門店に併設された直売所で説明を受ける
知事
牧野さんが野菜の生産にとどまらず、多角的な展開を目指す姿勢がすばらしいです。新たな挑戦を始めるきっかけについて是非お聞きしたいです。
まきの菜園&M's CURRY 牧野祥起さん
次世代のために、農業を続けられる形を目指しています。おいしい野菜があってこそのカレーであり、その品質を追求することで消費者の期待に応え、ビジネスの可能性も広げられると思います。魅力的で安定した経営を続けることで、次世代が挑戦したいと思える環境を整えたいです。
知事
近郊農業で収益を上げるには、JAへの卸売だけでなく、加工や直売、レストラン経営など多様な取組が重要です。皆さんが近郊農業で成功するために行政がどのような支援を行うべきか、是非皆さんの経験や御意見をお聞かせください。
株式会社ボニカ・アグリジェント 岡永代表取締役社長
情報共有の不足が大きな壁となっています。成功事例や失敗談を共有することは、新たな挑戦への後押しになります。また、生成AIやドローンなど新しい技術が登場しているものの、具体的な支援や情報が不足し、活用が進みにくいのが現状です。相談窓口を設け、幅広い支援や情報提供を行うことで、生産者が前向きに取り組める環境づくりが求められています。
株式会社TNfarm 石井代表取締役
農家間での情報量には大きな差があります。この情報格差を解消することで、情報交換が円滑に進み、時間のロスを最小限に抑えられます。また、情報窓口を明確にすることで、相談先が分からずに困るといった問題を解決し、より効率的な情報共有が実現します。
まきの菜園&M's CURRY 牧野和美さん
農家は家族経営が多く、栽培量や人材確保に限界があります。若い世代に農業の魅力を伝え、興味を持つ人を増やす取組が必要です。
株式会社TNfarm 石井代表取締役
人手が欲しいとは思うものの、質を落とすことなく、自分たちで確認していきたいという考えもあります。
知事
お話があった情報共有についてですが、ネットワークをどう作るかですかね。
株式会社ボニカ・アグリジェント 岡永代表取締役社長
ネットワークの構築はいいですね。
知事
埼玉県のフードパントリーネットワークは、ネットワーク構築の成功事例として挙げられます。この取組は、寄贈された米を融通し合うなど、実需に基づいた効果的な連携が行われています。
農業分野では、彩農(さいのう)ガールズという女性農業従事者のネットワークがあり、技術向上や共通の悩みの共有を目的とした活動が展開されています。
ネットワーク化に必要なアイデアを皆さんからいただければ、私たちもその連携を支援することが可能です。ただし、実需が伴わない場合は実現が難しいです。
農業の人材確保の課題は、繁忙期と閑散期の差にあります。これを解決するため、カフェ運営などで閑散期の仕事を確保し、繁忙期には農業へ人員を振り分ける方法があります。
また、DXによる効率化や「農福連携」による福祉事業所への作業委託も有効です。複数農家が共同で委託し、報酬を出来高制にする仕組みを構築すれば、農業と福祉双方にメリットが生まれ、相乗効果が期待されます。参考にしてください。
ページの先頭へ戻る
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください