ページ番号:272136
掲載日:2025年8月29日
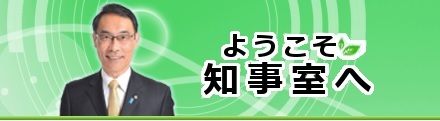
ここから本文です。
利根地域 (令和7年7月16日)
訪問日
令和7年7月16日(水曜日)
訪問地域
利根地域(行田市、羽生市、加須市)
訪問先
ものつくり大学(行田市)
|
ものつくり大学は、国、自治体、産業界の支援を受け2001年に設立された、高度な技能技術を追求する「テクノロジスト」の育成拠点です。 授業の6割が実習であり、実務経験豊富な一流の技術者の指導を受けながら、学内を現場に見立て学生自ら施設の改修を行うなど、実技を重視したカリキュラムが特徴です。 2024年にフランスで開催された技能五輪国際大会造園職種に出場した学生が銀賞を受賞するなど、各種技能競技大会で成果を残しています。 訪問先では、実習現場を視察し、教員や学生の方々と意見交換を行いました。 |
 |
|
学生のかんな技術を見学する |
知事
学生さんお一人ずつにお伺いしたいのですが、まず一つが御自分の目指す所。もう一つは、色々な教育機関がある中で、ものつくり大学を選んだ理由。そしてよかった所。その三つを教えていただければと思います。
里さん(ものつくり学研究科修士課程1年)
元々、ものつくり大学の情報メカトロニクス学科にいたのですが、一度中退し別の大学を出ています。本業の方で家庭教師をしており、こどもたちと接していく中で、教育用のAIを開発したいという思いから、ものつくり大学の大学院で研究しようと戻ってきました。
ものつくり大学は普通の大学と違って授業も幅広く、応用科目や実技が充実していて自分の理想の大学だと思います。機械、電気・電子・情報の分野を横断的に勉強できるのが魅力だと思います。
オウさん(情報メカトロニクス学科機械デザインコース4年)
ものつくり大学に入学したきっかけは、知識より実技が充実していたことです。自分はものづくりが好きなので、今は松本研究室に所属していて、先ほど見ていただいた3Dプリンターでものづくりを行っています。
田子さん(ものつくり学研究科修士課程1年)
私は高校のときから建築と造園、空間デザインを勉強していて、それを実際に施工できるようになりたいと思ったので、実務的な授業にひかれて入学しました。
学内に他職種で腕のいい子がいたり、今まで触れてこなかった技術も一緒に学べたりしたので、大学に入って自分の知らない世界が広がったと思っています。
篠原さん(建築学科建築デザインコース4年)
設計は好きだったのですが、私は元々文系を選んでいたので、自分には難しいのではないかとずっと思っていました。進路を決めるときに興味のある部分を伸ばすのが一番いいと両親や先生とも話し、建築を学ぶに当たって実技的に覚えていくのが得意と感じている部分もあったので、この大学は6割くらいが実技授業ということで、苦手なこともやっていくうちに覚えていくという思いからこの大学を選びました。
知事
入学してよかったですか?
篠原さん(建築学科建築デザインコース4年)
はい。すごくよかったなと思っています。先生方とも距離が近く、名前も覚えていただいて、他の大学よりもアットホームな雰囲気が自分には合っていると思います。
古舘さん(建築学科木造建築コース4年)
私は将来、住宅を造る木造の大工さんになりたくて、木造の実習をやるためにこの大学に入りました。また、造園や足場といった木造以外のことも一年生の頃から幅広くできるので、そういった部分にも魅力を感じました。授業では工務店で働いている大工さんが非常勤講師としていらしてくださり、普通は人に教えないような裏技なども、距離が近いからこそ教えてくださり、とても勉強になっています。
知事
一つの分野だけでなくほかの分野も一緒に色々な話が聞ける、経験ができるというお話がありましたが、他のフィールドで活躍されている人や先生方と触れるということは、御自分の経験や実技に大きな影響を与えるものですか?
里さん(ものつくり学研究科修士課程1年)
私はものつくり大学の宇宙開発研究プロジェクトに所属していたことがあるのですが、ロケット1本作るにも、機体も自分たちで設計してプラスチックを固めるところから作り、3Dプリンターを使ったり自動車技術等でもあるFRDを使ったりと、色々な技術をまとめないと作れません。
色々な学問だったりスキルを融合したりして一つのものをつくりあげられるのは、ものつくり大学だけだと思いますし、貴重な体験だと思います。
株式会社東亜酒造(羽生市)
|
株式会社東亜酒造は、江戸時代から続く創業400年の老舗酒造メーカーで、清酒「晴菊」が代表商品です。 |
 |
| ポットスチルを見学し、説明を受ける |
知事
日本酒やウイスキー、果実酒などバラエティーを持っているメーカーって埼玉県にはあまりないですよね。そういった意味では非常に珍しいと思いますが、その特色は御社の販売戦術にどのように反映されているのでしょうか?
仲田代表取締役社長
清酒だけを販売しているわけではないので、全てのカテゴリーのお酒を御案内ができるのが強みです。当社は輸出も少しやっていますが、清酒だけでなくリキュールやウイスキー、全部積み合わせできるのが強みだと思います。
知事
なるほど。ある意味商社さんのような。例えば羽生の飲食店に入って、羽生のお酒と言えば、いろいろ出てくるように。
仲田代表取締役社長
観光客を誘致しても、羽生蒸溜所だけで終わってしまうと羽生に滞在してもらえないので、羽生蒸溜所を見学した後に食事をできる所があればいいと思います。
知事
埼玉県の観光業の特徴として、泊まる所が目安として千葉や神奈川の3分の1です。東京の8分の1。泊まった方がお金になりますが泊まる所がない。これが埼玉県の特徴です。しかもものすごく交通の便が良いので、みんな帰ってしまう。ですので、食事をしてもらうことは重要です。
もう1つは、実は、観光業は人的集約産業で労働生産性がものすごく低いので、そこだけだと皆儲かりません。いかにお土産を買ってもらうか。その点、お酒は値段が張るのでとてもいいです。これを観光業にくっつけると労働生産性が上がる。それを埼玉県は今考えています。
仲田代表取締役社長
今や全国にウイスキーの蒸溜所が170を超えるくらいあります。20年前は16ぐらいしかありませんでしたが、一気に増えています。
ほとんどの蒸溜所は地方にあるので、東京から一番近い蒸溜所だと我々はうたっています。東京から一番近くて、駅から5分で来られる蒸溜所ですと。
電車で来られるので、テイスティングして帰れるということをうたっています。
知事
外務省にいたとき、フランスで仕事して半日空くとランスまで行きました。シャンパンを2本買うと500ドル。大体半日でそのくらいお金を落としていることになります。仕事で東京に来て、羽生蒸溜所を見て、お酒を買って帰ってくるっていうのは非常にいいですよね。
1年中あるいは何年も同じ味を出していくのはすごく難しいのではないかと思いますが秘訣はありますか?
横地生産本部蒸留課兼営業本部直販課リーダー
秘訣と言われるとあまりないかもしれませんが、日々できたものをテイスティングして、ブレがないようにしたいところです。
知事
それは舌が頼りですか?数字があるのですか?
横地生産本部蒸留課兼営業本部直販課リーダー
アルコール度数などは数字があります。
仲田代表取締役社長
もっと言いますと、かつて蒸溜していたときに作業していた社員が残っていて、その社員が当時を思い出しながらやっています。
また、その当時の製造記録が全部残っていたので、アルコール度数がどのくらいで発酵するかといった記録も残っていました。
ただ、設備もよくなったので、昔の製造記録と同じようになるわけではありません。
同じ敷地内で製造・貯蔵しても、気候変動の影響で昔とは違います。
知事
発酵の速度も変わるでしょうね。
仲田代表取締役社長
変わります。製造記録を参考にしながら、それをどんどんブラッシュアップしています。
知事
本当においしかったです。ありがとうございました。
渡良瀬遊水地周辺における地域活性化の取組(加須市)
|
加須市北川辺地域は、ラムサール条約登録湿地で広大な自然が楽しめる渡良瀬遊水地や、全国でも珍しい「歩いて行ける三県境」などの地域資源に恵まれています。 |
 |
|
熱気球のゴンドラに試乗し、説明を受ける |
知事
市とウム・ヴェルトは協定を結んでいるのですか?
加須市 角田市長
市とFMわたらせも防災時の緊急放送について協定を結んでいます。このほか、今村さんのSOLAとウム・ヴェルトが共同で、ウム・ヴェルト株式会社、道の駅かぞわたらせ、FMわたらせのロゴが入った気球をつくりました。
株式会社SOLA 今村代表取締役
気球のいい所は、お金に代えられない価値がある所です。乗れたときの感覚は金額に換算できる以上のもので、五感で感じる感覚を感じさせてもらえるいいものだなと。
加須市 角田市長
今村さんのSOLAでは、空き家の納屋を宿泊施設にして、グランピングもやっています。コテージも最近つくって、年間500~600組、全国から気球で飛ぶために泊まりに来ています。
知事
一番多いときはどのくらい泊まるのですか?
株式会社SOLA 今村代表取締役
最大の人数は20人ですが、気球に合わせて大体週末に16~18人くらいですね。
気球以外にも、たき火、キャンプ、サイクリング、その日だけの気軽なアクティビティをしに来る人がちょこっと泊まり、拠点として使える場所。日帰りだと往復の運転に少し疲れてしまうのでちょっと拠点に泊まりたいという需要がこの辺りはすごくあって。スポーツがここの地域では全てできるのは、一つのポテンシャルかなと。
知事
FMわたらせをどうしてここでやろうと思ったのですか?
ウム・ヴェルト株式会社相談役 兼 株式会社わたらせコミュニティメディア
小柳代表取締役
道の駅をやることになり、この建物の有効活用はないかと思っていました。
実は宇都宮のコミュニティFMにも出資していましたので、ここでFMをやれば少しは加須市の皆さんの役に立つかなという思いでスタートしました。
また、令和元年度の台風19号のとき、非常に危機的な気持ちになりました。北川辺地域は加須のまちなかへ行くにも、橋を渡らないといけませんが、橋は一つしかなく大渋滞。もう少し早い時点で、どこに行ったら一番いいのかということを含めて、もっとローカルな情報をFM放送で流せばあんな大変なことにはならなかったのかなという思いもありました。