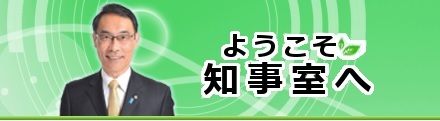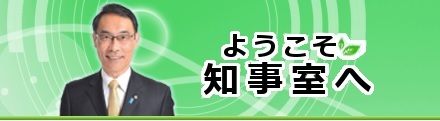こどもたちが生き生きと遊んでいる姿を拝見して、とてもうれしく思いました。特に滑川町は、こどもが多いところでもあり、このような伸び伸びと、そして先生方が工夫をされておられるこども園があるというのは大変うれしく思います。すごく面白いと思ったのは、育児担当保育者の制度で、非常に興味を持ちました。大体0歳から2歳までとおっしゃっておりましたが、保育士お一人当たり何人を受け持っておられるのですか。
0歳については3人のお子さんに対して1人の保育者、1歳に関しては4対1で、2歳に関しては6対1で、その担当保育者以外に各グループに1人の介助の保育者が入っています。現在、0歳のお子さんを6人お預かりしており、担当保育者2人と、1人の保育者が介助で入っています。1歳のクラスでは、担当保育者が6人で、2人の介助の保育者が入っています。担当保育者が1人のお子さんに食事を与えているときに、介助の保育者が他のお子さんたちを見て、連携しながら保育をするという形で運営しております。生活の場面である、食事・排せつ・睡眠・着替えについては、1対1や2対1で丁寧に担当保育者が関わっていきます。
お二人はこの園の卒園生と伺いました。御自身が関わられた先生への愛着がすごく深いのではないかと思うのですが、その辺は御自身のこれまでの人生形成にとってプラスになっていますか。
とても自信を持って生活することができています。ハルムこどもえんの先生にあこがれて保育士を目指したので、その夢をかなえることができて、とても幸せに暮らしています。
保育園に通っていたときの先生を今でも覚えていて、その先生は今でも働いていらっしゃいます。親の代わりみたいな存在がいるのは、なかなかないことだと思うので、この保育園は本当にすばらしい保育園だなと感じています。私もハルムこどもえんの先生がきっかけで保育士を目指し、就職を決めました。
妊娠、出産を経て、御自分のお子さんをハルムこどもえんの系列園に預けながら仕事を続けてくださっている方も多いです。お子さんは保護者の方と違う園でお預かりをしていますが、同じ理念で保育をしてもらえるので、お子さんを安心して預けてくれているのかなと思います。
リズムの形成について、それぞれの御家庭の時間をお伺いして、その子なりのスケジュールを作っていくというお話がありました。こどもの頃の時間形成、スケジュール感覚はすごく大切です。親が不規則な時間帯で過ごしているこどもは、家庭主導の時間のリズムを受け入れてそのままにするのか、又は、園である程度他の子と合わせてリズムを作っていけるようになるのか、その辺はどのように考えていらっしゃいますか。
月齢・年齢によって、どのくらい睡眠を取ったらよいかは、生理学的に証明されていますので、そういったエビデンスを保護者会で示しています。夜の睡眠時間は、脳の発達や身体の発達に大変重要になってくるということを説明して、どのくらいの睡眠時間の確保が必要かということを伝えています。お子さん中心の生活が大前提で、それに応じて1、2時間の多少の誤差を私たちは調整して、お子さんたちのリズムを整えていきます。
株式会社NONIWAは、都内からときがわ町へ移住した夫婦が経営する企業で、キャンプ体験型民泊施設の運営や、アウトドアグッズ等の販売などを行っています。
体験型民泊施設「NONIWA」では、インストラクターの充実したサポートにより初心者でも気軽にキャンプができる環境となっています。また、女性1人でも安心して利用できるよう会員制を採用しています。
アウトドアグッズの販売を行う「GRID」では、既成製品だけではなく、地域とコラボレーションした商品の販売なども行っています。
地元事業者と協力して「ときがわアウトドア協議会」を設立し、地域の文化にアウトドアの要素を組み合わせて、ときがわ町の魅力発信にも努めています。
訪問先では、「NONIWA」及び「GRID」を視察するとともに、経営者やアウトドア協議会の会員の方々と意見交換を行いました。

GRIDでアウトドアグッズについて説明を受ける
知事
大変面白い試みを勉強させていただきました。先ほど移住をされるときに、ネットでときがわ町を調べて来られたという話がありましたが、実際にときがわ町に来られたときに、何がいいなと思われたのか教えていただけますか。
青木代表取締役
移住への不安はありましたが、ときがわ町なら移住できるかもしれない、受け入れてもらえるかもしれない、という印象を受けました。移住者コミュニティが固まっていなくて、それぞれが個々に頑張っている感じがよかったです。ときがわ町だったら、自分たちも頑張れるかもしれないと思いました。また、ときがわの山と川がゴツゴツしていなくて、かわいらしいなという印象を受けました。
青木取締役
私は「楽や」という農家民宿に通っていたときにいろいろな人を紹介してもらい、その人たちの自由さやおおらかさがいいなと思いました。皆さん、自由だけどちゃんと助けてくれる環境が良かったです。
知事
緩やかな連携はあるけれど、がっちりしていないイメージでしょうか。アウトドアフェスは、ときがわアウトドア協議会としてやっていらっしゃいます。皆さんの思いとして、このイベントをきっかけに関係人口を広げていく、リピーターを増やすようなイメージでしょうか。
青木代表取締役
「ときがわとつながる」ことをテーマにしています。移住者も、まだ、ときがわの深いところや地元の人と知り合えていないこともあるので、このイベントをきっかけに仲良くなれるというのもあります。同時に、ときがわ町に興味があるので行ってみよう、というきっかけにもなってほしいという思いがあります。このイベントを通じて、いろいろなつながりが持てるようにというところは、1つの大きなテーマにしています。
知事
関係人口を広げていくには、二つの方法があると考えており、宿泊してもらい、その地域を深く味わってもらうのが一つ。もう一つは、交通の便がいい「トカイナカ」の埼玉県は、交通の利便性があるからこそ、東京から通えて同時に東京まで帰れますので、泊まってもらうパターンと、日帰りでしっかり楽しんでもらうパターンと、両方ありではないかなと私は思っています。いいところをどう組み合わせるかで、この地域の魅力をプラスにしてくれるのではないかと思います。
ちなみに、関和さんも松本さんも地元の人で、自分たちと全く違う発想でときがわを見て、違う文化の人たちが中に入ってくるようになるといろいろあると思うのですが、その辺の反応は上の世代も含めてどうですか。
GEMS GRILL 関和代表
自分たちの少し上の世代は、意外と肯定的な人が多いのですが、年配の方はやはり「何をやっているのか分からない、あそこで何か始まったけれども、何なのだ」というような反応はありました。そもそもこの協議会を、地元の人間が立ち上げて地元の人間だけでやっていたら何の面白味もないし、知名度も低い。だからこそ、この2人の力を借りたかったというのもあり、その力は非常に大きいです。
有限会社松本建設 松本代表取締役
元々地元にいる我々が間に入れたらいいかなと思っていて、地元の人たちに「こういう人たちがこういうことをやっているのですよ」というような形で、協議会がその間に入って、窓口的な役割を担えればと思っています。
ページの先頭へ戻る
地球観測センター
地球観測センターは、「リモートセンシング技術」の確立・発展を目指して宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開設した施設です。
地球観測衛星「だいち2号」や「だいち4号」からのデータを受信して「筑波宇宙センター」へ送信する役割を担っています。
センターには、一般公開されている施設もあり、地球観測の意味や仕組みを学ぶことができます。
管理・運営を行っている一般財団法人リモート・センシング技術センター(RESTEC)は、東松山市などの近隣市町と協定を締結しており、地域課題の解決にも貢献しています。
訪問先では、地球観測センター内の施設を視察するとともに、JAXA及びRESTECの職員と意見交換を行いました。

モニタールームで衛生受信データの説明を受ける
知事
我々地方自治体ですと、どうしても災害などが一番気になるところです。中でも、最近特に我々が問題意識を持っているのは、いろいろなステークホルダーの中でどうやってその情報プロトコルを共通化するかということです。どれだけ早いスピードで災害対応をするかを決めていくということが、非常に気になるところであります。先ほどの防災関係機関と衛星データを共有する防災インターフェースシステムというものがありました。これは各ユーザーで共通するものなのか、あるいは、ユーザーのニーズに従い個々に提供し、地球観測センターで提供するデータの精度についてプロトコルを工夫しているものなのでしょうか。
JAXA 滝口理事
データの受渡しと人の問題です。災害の最中に衛星情報を渡したところで、のんびり画像を見ている場合ではなく、差し迫った状況であると。解像度を細かくした方がむしろ商売になるので、我々は民間とのコンビネーションを大事にして、官民のコンソーシアムの中の連携チームとして、防災活動を行う取組を始めたところです。防災庁も、自治体とつながってちゃんと運用できるプラットフォームの構築を並行して進めていると聞いています。そのプラットフォームの上に衛星画像を載せていきたいと思っています。こちらから防災庁に精細なデータをどうやってお渡しするかについてですが、データを渡すのではなくて情報を出さないといけない。アラートだけマーキングして、その情報をお渡しするような仕組みとか、いろいろな工夫をもう10年以上やっています。
知事
私の方から1つお伺いしたいのが、今もちろんこういう御時世ですから支障がないのかもしれませんが、筑波とここ地球観測センターで、地理的な関係や施設の関係、又は運用やその指揮命令について、何か支障があったりしますか。
JAXA 滝口理事
最近は、ほとんどITテクノロジーでリモート制御できますので、そういう物理的な距離の支障はないです。
地球観測センター 藤澤所長
今は筑波在勤ですが、コロナ禍を受けて、やはりネット環境、例えばオンラインでの会議やテレワークも普及しましたし、通常業務をする上で距離が遠くて業務に支障が出ることはあまりありません。計算機もリモートコントロール化されていますし、今はクラウド化が進み、筑波宇宙センターにもほとんど計算機がない状態です。もちろん一部はありますが、民間のAmazonやMicrosoftアジュールなどいろいろありますので、そちらの計算機クラウドを活用するようなことが増えています。
知事
JAXAさんは、多分、仕事はあまり変わらないかと思うのですが、逆に地元のRESTECさんの方が一部変わってくるようなイメージですか。いかがでしょうか。
RESTEC 坂田理事
基本的にはそんなには変わらないです。やはりリモートで我々もやらないといけないこともありますので、そこは便利になっていると理解しています。実は筑波にも同じような部門がありますので、筑波との連携も結構リモートでやっています。ただ、やはり現場ででしかできないことはあります。例えばここですと、アンテナのメンテナンスは実際に現場に来ないとできないですし、運用室に来てやらなくてはいけないこともあります。
ページの先頭へ戻る
鈴茂器工株式会社川島テックプラント
鈴茂器工株式会社は、世界で初めて寿司ロボットを開発し、寿司ロボットのトップメーカーとして大手回転寿司チェーンのほぼ全てに製品を納入しています。
「海苔巻き」「おいなり」「おむすび」「御飯の盛り付け」など米飯に関するロボットも幅広く開発・製造しており、低コスト化や人手不足の解消に貢献しています。
海外の日本食ブームに対応して、世界80か国以上にロボットを輸出しており、売上高も拡大を続けています。
埼玉県SDGsパートナー企業に登録するなど県の施策にも協力していただいています。
訪問先では、工場内を視察するとともに社員の方々と意見交換を行いました。

シャリ玉ロボットのデモンストレーションを受ける
知事
川島町のみならず、鶴ヶ島工場もオープンしていただくということで、埼玉県に拠点を構えていただき、加えて多くの雇用や、驚きも含めて「おいしい」「暖かい」をお届けいただいているということで感謝申し上げます。海外に米飯や寿司を広げるきっかけになるようなものを出していただくと、いろいろな食材が日本から海外に広げられると思っております。特に食品加工業について、埼玉県は日本でナンバーワンでございますので、その付随の効果として、埼玉県にも大きなプラスの効果があるということで感謝申し上げたいと思っています。まず、鶴ヶ島工場のオープンを決めたということで、埼玉を選んでいただいた理由を伺えればと思います。
田頭執行役員生産本部長
小型機器の生産をこの工場から鶴ヶ島に移管する予定ですが、今働いている方々を継続的に雇用していくことが大前提であり、通勤ができる地域というところが鶴ヶ島を選んだ理由です。
知事
実は去年、日本で一番多く本社に来ていただいた県が埼玉県なのですが、必ず言われるのは、人手が足りないということです。その一方で省人化や、様々なデジタル化等を含めて、いろいろな工夫が必要だと思うのですが、御社の場合、省人化については具体的にどのような取組をされておられますか。
田頭執行役員生産本部長
省人化に関しては、我々が機械を供給したスーパーさんや加工業者さんの省人化がメインです。工場での生産については、鶴ヶ島工場もありますので、いろいろなIT技術を導入しながら技術者の効率化を図り、分業化するなどしてその生産性を上げたいと考えています。
知事
お取引先が食べ物を扱うメーカーさん、特にBtoCのところが多いのだろうと思いますが、今、食材の価格がどんどん上がっている状況で、彼らのコストカットの意識も強いと思っています。こういった機械に対するお取引先の投資需要や投資意欲というのは、どうお考えですか。
田頭執行役員生産本部長
日本国内は、やはり少し抑え気味になっています。ただ、実際には売上げを伸ばしていて、我々の機械を使うことによる効率化の方に、どちらかというと前向きな感じが全体としてはあります。これからですと、北米などで日本食ブームの広がりもありますので、需要が拡大していくのではないかと思っています。需要の拡大が想定されるので、鶴ヶ島工場も建てて、生産量を拡大していくという流れになります。
知事
こういった寿司のシャリ玉については、恐らく海外でこれからどんどん増えていく余地がすごくあるのだろうなと思うのですけれども、海外展開は商社さん、あるいはその現地法人、あるいは代理店とどういうイメージでいらっしゃいますか。
田頭執行役員生産本部長
まず、アメリカとシンガポールに直接の拠点がございます。そこを中心に北米とアジア圏を対応しまして、ヨーロッパや他の地域は販売代理店で対応しています。我々の機械は、ただ売っておしまいではなくて、売った後のメンテナンスも含めたサービスも大事になります。機械を使っていると消耗してくる部品とか、壊れたときなどを含めて対応しており、日本では日本のサービス拠点で対応し、海外では海外の代理店にサービスも含めて対応をお願いしています。しかし、国によっては更に拠点を開拓していかないと拡販が難しいので、そこに関してはこれからの課題だと思っております。やはり海外からの引き合いが多いので、造る力を増やしていきたいということで、正に鶴ヶ島の立上げをいかにスムーズに行っていくかということも直近の我々の課題として認識しています。
知事
我々としても埼玉県の特色は交通の便だと正直思っていますので、鶴ヶ島もそうですが、今後もより便利になっていきますので、またいろいろとお使いいただければと思っています。
ページの先頭へ戻る
武州瓦斯株式会社水産研究所
武州瓦斯株式会社は、事業の多角化と埼玉県でのうなぎ文化の盛り上げを目指して、令和4年6月にうなぎ養殖事業を始めました。
独自のろ過システムにより排水量を最小限に抑えるなど、環境に優しい陸上養殖を実現しています。
商標登録もされている「武州うなぎ」は、インターネットで販売されているほか、東松山市のふるさと納税返礼品にもなっています。
訪問先では、水産研究所を視察するとともに養殖に関わっている同社の方々と意見交換を行いました。

うなぎの餌やりを見学
知事
先ほど大変貴重なレプトセファルスからシラスウナギになったうなぎを見せていただきありがとうございました。もう何十年もやっていませんが、多分47都道府県でただ1人、うなぎの目打ちができる知事でございます。
すごく面白いなと思ったのが、ヒートポンプでの水温調整とか、ろ過利用。エネルギー企業らしいうなぎであることにすごく感心をいたしました。いわゆるヒートポンプでの熱交換なども含めて、こういったシステムのアイデアは、施設の周囲も含めて、どうしてあのような形にされたのでしょうか。
大河原チーフマネージャー
養殖事業をやろうと決めたときに、さいたま市にあるサイエンスイノベーションさんから、うなぎにはこういうシステムがいいですよと一式を御紹介いただいて、それを勉強させていただき、いいなと思ったので納めていただきました。今回お見せできなかったのですが、クッションタンクみたいなものを用意しており、冷熱と温熱を両方一気に出すと使えるようになっています。冷熱と温熱を両方一緒に取れるのがサイエンスさんのヒートポンプだったので、それもいいなと思い採用しました。
原常務取締役
電気代は、やはりある程度掛かってしまいます。サイエンスさんからだけでなく、我々からも太陽光発電を提案させていただいて、太陽光発電で賄えるとまではいかないのですが、電気代を少し抑え、環境整備のところは考えながらやっています。でも、まだまだ電気代はかなり掛かってきてしまっています。
知事
屋内でこれだけのことをすると相当投資コストが掛かるだろうし、大変だなと思いました。正にチャレンジがすごいなと思いましたし、是非、埼玉県でうなぎの養殖から輸出までしていただければと思います。
アンモニアのコントロールはどうされていますか。一気に上げると死んでしまうし、餌由来と排せつ物由来の両方があるじゃないですか。抜き取りでやっているのですか。
大河原チーフマネージャー
アンモニアは、餌をあげる前に測定しています。pHが落ち過ぎてしまうと亜硝酸中毒にもなってしまうので、ちゃんと管理しています。アンモニアと亜硝酸のpH環境を、試験材を使って拭き取りでチェックしています。ノウハウが蓄積されているかというと、まだまだこれからです。
知事
ちなみに今、こちらの部門で働いてらっしゃるのは何人くらいですか。
大河原チーフマネージャー
ローテーションで回していて、販売も販路開拓も含めて6人でやっています。
知事
武州うなぎは、冷めても、皮もきちんとかみ切れますし、おいしくいただきました。ありがとうございました。
ページの先頭へ戻る