ページ番号:3579
掲載日:2024年12月12日
ここから本文です。
食中毒関連情報
食中毒予防の3原則
食中毒とは、有害な細菌やウイルス、化学物質等が食品とともに体内に入りこみ、健康被害を引き起こすことをいいます。
症状は、下痢やおう吐、発熱など原因によってさまざまで、重症化したり死に至ることもあります。
食中毒を起こさないために、食中毒予防の3原則を徹底してください。
「つけない」
誰の手でも、どんな食材でも、食中毒菌がついている可能性があります。
汚染された手指や調理器具を介して、他の食品に菌をつけてしまうことを「二次汚染」といい、食中毒の原因になります。
生で食べる野菜や調理済みの食品に菌を「つけない」よう、次のことに気をつけましょう。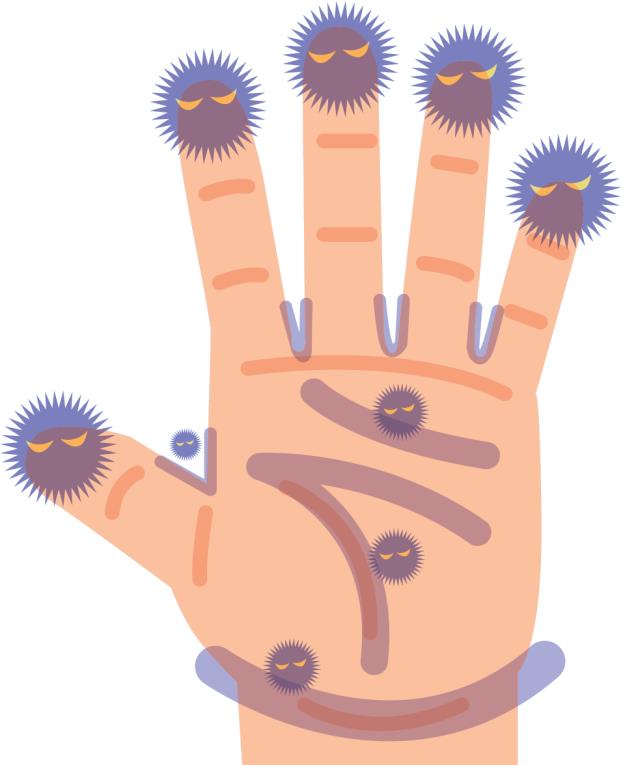
- 手洗い
調理や食事の前、トイレの後にはしっかり手を洗いましょう。
水洗いの後、石けん洗いとすすぎを2回繰り返す「2度洗い」が効果的です。
- 使い分け
調理器具や布きんは、食材ごとや、加熱前と調理済みの食品で、使い分けましょう。
使い分けが難しい場合は、取り扱う食材や作業の内容が変わるときに洗浄・消毒を徹底しましょう。
「ふやさない」
食中毒菌の多くは 10 ~ 50 ℃で増殖するため、要冷蔵品や調理済みの食品を室温で長時間放置するのは危険です。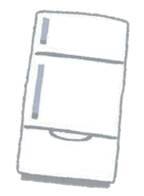
食品を保存する場合には、菌を「ふやさない」ように、小分けにして速やかに冷蔵庫で保管しましょう。
食品を「10℃以下」に保つために、冷蔵庫内は詰めすぎないようにし、扉の開閉はなるべく少なく、短時間で行いましょう。
「やっつける」
食中毒菌の多くは熱に弱いため、加熱することで「やっつける」ことができます。
食材の表面だけではなく、内部にまで菌が潜んでいることがあるため、食品の中心部まで十分に加熱しましょう。
- 加熱の目安 中心温度 75 ℃で 1 分間以上(ノロウイルスの対策には 85 ~ 90 ℃で90 秒間以上)
食中毒発生状況
過去3年次の埼玉県全域での食中毒発生状況
※( )は患者数
| 令和3年次(2021年) | 令和4年次(2022年) | 令和5年次(2023年) | |
|---|---|---|---|
| ノロウイルス | 1件(79名) | 2件(38名) | 4件(78名) |
| カンピロバクター | 3件(10名) | 6件(24名) | 6件(25名) |
| 腸管出血性大腸菌 | ー | ー | 1件(14名) |
| その他の大腸菌 | 1件(178名) | ー | ー |
| サルモネラ属菌 | ― | 1件(110名) | 2件 (7名) |
| ウエルシュ菌 | 4件(473名) | ー | ー |
| 黄色ブドウ球菌 | ー | ー | ー |
| アニサキス | 9件(10名) | 10件(10名) | 5件(5名) |
| 化学物質 | ー | ー | ー |
| 植物性自然毒 | ー | 3件(7名) | ー |
| 動物性自然毒 | ー | ー | 1件 (1名) |