ページ番号:275370
掲載日:2025年11月21日
ここから本文です。
危機管理・大規模災害対策特別委員会視察報告
調査日
令和7年7月22日(火曜日)~ 23日(水曜日)
調査先
⑴茨城県地域気候変動適応センター(水戸市)
⑵かみす防災アリーナ(神栖市)
調査の概要
(1)茨城県地域気候変動適応センター
(災害対策における気候変動への適応推進について)
【調査目的】
■本県の課題
- 近年、気候変動の影響により激甚化・頻発化している気象災害から県民の生命や財産を守る必要がある。
■視察先の概要と特色
- 地球温暖化や気候変動の影響に対応するため、「気候変動影響及び適応に関する情報の収集、整理、分析、提供、技術的助言を行う拠点」(気候変動適応法第13条)として、茨城県が事業者として茨城大学地球・地域環境共創機構を選定し、茨城大学に設置された。大学を事業者とするセンター設置は全国初である。
- 茨城県をはじめとする県内の自治体や各種団体や学校、住民と協力して気候変動・温暖化の影響やその適応のための様々な情報を収集・解析し、広く発信している。
- 地域における気候変動影響・適応に関する研究として、災害等の気候変動影響予測を行い、また、ローカルな情報収集では、農業・漁業、防災関係者等へのインタビュー、アンケート調査等を行っている。
【調査内容】
■聞き取り事項
- 大学であることのメリットを生かし、科学的な知見に基づいた上意下達型の知識の伝達を行うこと、また、ステークホルダーとのやり取りで、まず現場の情報把握を行い、そこから何が必要なのかを組み立てることの両方のアプローチにより、業務を進めている。
- 避難行動に関する研究において、2年に1度くらいのペースで河川が溢れ床下浸水の被害が起こる地域で、大雨の際に、過去の経験から避難しなかったが、河川が決壊してしまい避難が間に合わなかったという事例があった。これは、過去の被災経験はとても大事だが、それに囚われてはいけないということである。
- 行政のソフト対策に対するサポートとして、シンポジウムを開催している。例えば、気候科学のプロフェッショナルを講師として招聘したり、気象台との協力関係で防災士を集め、コミュニケーションを図るなど、センターの強みを生かしている。
■質疑応答
Q:行政側が施策を実現する際に、研究の情報を共有することは大事だと考えるが、研究者の立場から配慮しているようなことはあるか。
A:実際に河川の予測情報を出すとなると、気象業務法にのっとることになるが、その議論が進んでいる段階である。雨の予測が難しく、その精度を上げていければ、気象業務法の許可も出て、様々なところから情報が出てくると考えられるため、活用が期待できる。
Q:避難情報などの伝達について、研究者の立場から具体的な考えや提案はあるか。
A:避難行動を最も後押しするのは声掛けである。特に消防団の声掛けで避難が進んだという調査結果もあるため、是非消防団は大事にしてほしい。また、デジタルコンテンツについては、地域によってなかなか見てもらえていないが、5年から10年もすればもっと活用されると考える。一方で、デジタルコンテンツの指示を避難しないことの理由にされてしまうこともあるため、頼り切りにはすべきでないことを強調したい。
(2)かみす防災アリーナ
(防災アリーナの運営について)
【調査目的】
■本県の課題
- 被災後の迅速な復旧・復興を見据えた事前準備など、全ての人々が安全で持続可能な暮らしを確保できるように危機管理・防災体制を構築する必要がある。
■視察先の概要と特色
- 計画段階から防災施設となることを想定し、運営・維持管理、学術的な知見も盛り込み、実状に沿う生きた避難マニュアルを作成している。また、建設中においても仮囲いや移動家具を活用したワークショップを開催し、市民に愛着を持ってもらう工夫が行われた。
- 平常時には安全・安心な環境の中で、スポーツ等を通じた市民の健康づくりに寄与し、各種イベントの開催により、多くの人が集い、市の中心部にふさわしいにぎわいを創出している一方、災害時などには温水プールを生活用水に活用するなど、避難所施設としての機能確保も図っている。
- グッドデザイン賞やウッドデザイン賞などを受賞しており、従来、閉鎖的になりがちであった防災施設が「軽快で美しいものに仕上がっている」との評価を受けている。
【調査内容】
■聞き取り事項
- 当初は4階層で検討していたが、各施設の配置を工夫して2階層とし、共有部分を1階公園側に集中配置して「コミュニケーションコリドー」と名付けた。長さ170メートル、幅10メートルの吹抜け空間であり、ガラス扉を自由に開閉できるため、様々な避難場運営、初動対応に合わせて、人の動きを自由に制御できる仕組みとなっている。
- 災害時への対応として、雑用水については、プールの水や雨水貯水槽を活用できる。また、下水本管破断時も、トイレ排水を緊急排水槽に排水可能である。そのほか、プロパンガスの残存分を炊き出しに活用することなどが可能である。
- 全てのトイレが停電時に水を流せる自己発電型となっている。また、トイレの照明についても、非常用発電機から電力が供給される。
■質疑応答
Q:総事業費のうち施設整備費121億円について、国、県及び市の負担割合はどうなっているのか。
A :国土交通省所管の社会資本整備総合交付金事業の交付金が入っており、約22億7千万円、率にするとおよそ21%の支援が国からあった。残りは全て市の負担となっており、県費は含まれていない。
Q:施設の中のトイレの便器の総数はどれくらいか。
A:およそ100個の便器を有している。東日本大震災の際に液状化の被害などがあり、トイレの問題は痛感している。メインアリーナの四隅のトイレにおよそ50から60の便器を設置し、また、1階の各所にもトイレがあり、それらを合わせるとおよそ100となる。また、屋外に手ごきの井戸のポンプがあるため、そこに手動で流すことが可能な仮設のトイレを設置することもできる。
Q:現在、土地の所有者は半分が国とのことだが、元々はどうであったのか。
A:元々は全て国有地で30年間使われていなかった。合併で神栖市となった際に、防災の拠点を作ろうということで、計画を進めていった経緯がある。
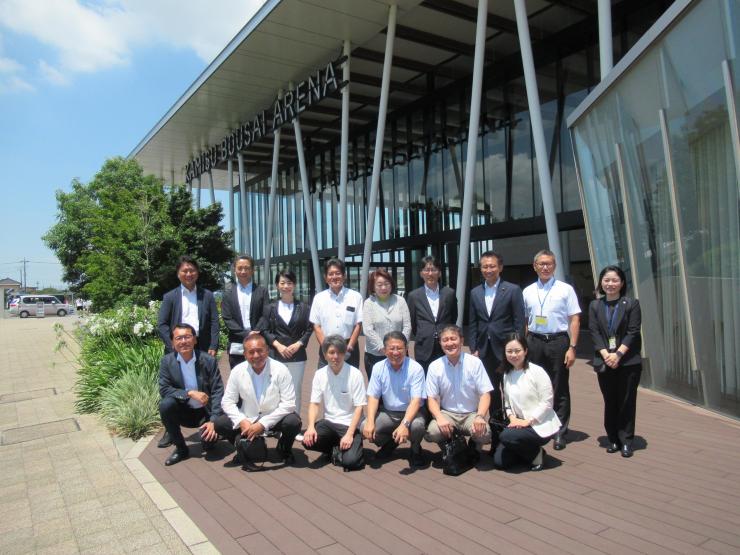
かみす防災アリーナにて