ページ番号:272447
掲載日:2025年9月17日
ここから本文です。
文教委員会視察報告
調査日
令和7年5月27日(火曜日)~28日(水曜日)
調査先
(1)福井県立恐竜博物館(福井県勝山市)
(2)加賀市立東和中学校(石川県加賀市)
調査の概要
(1)福井県立恐竜博物館
(特色ある社会教育施設(博物館)の運営について)
【調査目的】
■本県の課題
- 県民が身近に学び文化に親しむとともに、生涯学習の拠点となる博物館について、県民及び時代のニーズに合ったより魅力的な運営が求められている。
■視察先の概要と特色
- 福井県の有する恐竜資源を活用した地質・古生物学博物館で、特徴的な展示により来館者数は国内最大級の規模を誇る。
- 50体の恐竜全身骨格をはじめ千数百もの標本などの特徴的な展示により、こどもから大人まで楽しんで学習でき、研究者も学術的に満足できる展示を目指している。
- リニューアルオープンでは、実物大の恐竜世界を映し出す3面ダイノシアターや、化石発掘、骨格組立てなどの恐竜研究を体感できる化石研究体験室などの新たな機能を追加した。
- 学校教育支援として、博物館で活用できるワークシート、研究員による「恐竜授業」、教材として活用できる「恐竜博物館画像ライブラリ」なども充実している。
【調査内容】
■聞き取り事項
- 平成12年7月開館当初は30万人程度だった来館者数だが、平成21年に観光営業部へ所管移動し、広報活動を強化したことによって、平成27年以降に来館者数100万人に近づき、令和6年には126万人超を記録した。
- 面積4,500平方メートルの常設展示室では、約1,800点の標本を展示している。
- 展示以外にも、一般来館者を対象とした講演会、研究員による研究成果発表、博物館内ライブラリー整備など多様な活動を実施している。今年4月に開学した福井県立大学恐竜学部との合同講演会なども開催した。
- 学校団体向けの教育支援プログラムを用意し、ワークシートの提供、研究員による「恐竜授業」、標本貸出しなどを行っている。プログラム冊子は北陸の学校を中心に、日本全国の一部学校にも送付し、学習活動に活用されている。
- 今後も入館者数を更に増加させるため、広報活動強化、学校団体向けプログラムの充実、地域社会との連携強化などに取り組み、博物館の役割をより一層高めている。
■質疑応答
Q:学校教育現場との連携をどのように構築しているのか。
A:学校からの利用申込に基づき、学校が作成する教育活動計画に合わせたプログラムや資料を提供している。広報活動として、教育旅行プログラムを造成する旅行会社を通じた博物館の教育普及も行っている。
Q:福井県の学校教育で、博物館がより活用されるために、どのような取り組みをしているのか。
A:福井県内の学校が教育活動で来館する際には、観覧料を免除している。また、来館いただくほか、「どこでも恐竜授業」では、職員が出向いたり、オンラインでも活用いただいている。
Q:県外の博物館などの施設とは、どのような連携をしているのか。
A:全国各地の博物館と連携協定を締結し、研究・調査、講演の講師派遣などで連携している。
(2)加賀市立東和中学校
(ICT教育の推進について)
【調査目的】
■本県の課題
- 新しい時代に求められる資質や能力の育成が必要とされる中、ICTを活用した新たな教材や学習活動などを積極的に取り入れた、技術革新に対応する教育の推進が求められている。
■視察先の概要と特色
- 加賀市は、令和5~7年度の学校教育の方針を示す「加賀市学校教育ビジョン」を策定し、「BE THE PLAYER(自分で考え 動く 生み出す そして社会を変える)」をスローガンに掲げ、「そろえる」教育から人と違う強みを「伸ばす」教育への転換に取り組んでいる。
- 「小中一貫型加賀STEAM教育プログラム」では、プログラミング教育を小学校1年生からスタートし、9年間で探求的な学び、課題解決型の学びを身に付ける。
- 加賀市立東和中学校では、STEAM教育の一環として、生成AIの活用や地域連携による課題解決などの授業に取り組んでいる。
【調査内容】
■聞き取り事項
- 同ビジョンの主軸として「学びを変える」プロジェクトを推進し、一人一人に合った個別最適な学びと、対話を大切にした協働的な学びを目指している。指導主事やプロジェクトマネージャーが伴走型で教員研修を実施したり、外部専門家の支援を活用したりすることで、学校や生徒の状況に応じた対応が可能となっている。
- STEAM教育は、こどもが自ら考え、新しいものを生み出し、社会をより良くする力を育む学びと位置付けており、プログラマーなどの専門家を育てるというものではない。毎年、STEAM教育の成果発表プレゼンテーションの機会を設けている。
- 同校では、教育目標の実現に向けて生徒に身に付けて欲しい力として、「未来を創造する力(自立・共生・貢献・創造)」を掲げている。
- 授業づくりをする教員の負担軽減のため、教材研究の時間を勤務時間内に確保している。ICTの活用については、より効果的に活用できるよう、その使用を工夫している。
- こどもたちからは「これまでの授業では、分からなくなると諦めていたが、友人と協力して進めることで理解が深まった。自分のペースで学ぶことで、最後までやり遂げられた」などといった声が寄せられている。
■質疑応答
Q:プロジェクトマネージャーとはどのような人材なのか。
A:市教育委員会が採用し、学校の負担軽減やビジョン推進を支援するため、各学校からの要請に応じて訪問している。令和6年度は3名を採用した。
Q:生成AIなどのICTを活用した授業は、技術の教員免許を持つ教員が担当するのか。
A:必ずしも技術専門の教員が担当するわけではない。外部専門家の支援を活用したり、プロジェクトマネージャーと協力して授業づくりをすることで対応している。
Q:ビジョンの成果検証はどのように行うのか。
A:ビジョンは達成目標を設定するものではなく、方向性を示す「羅針盤」として位置付けられている。その上で、3年間でどのような変化が生まれたかを検証していく。
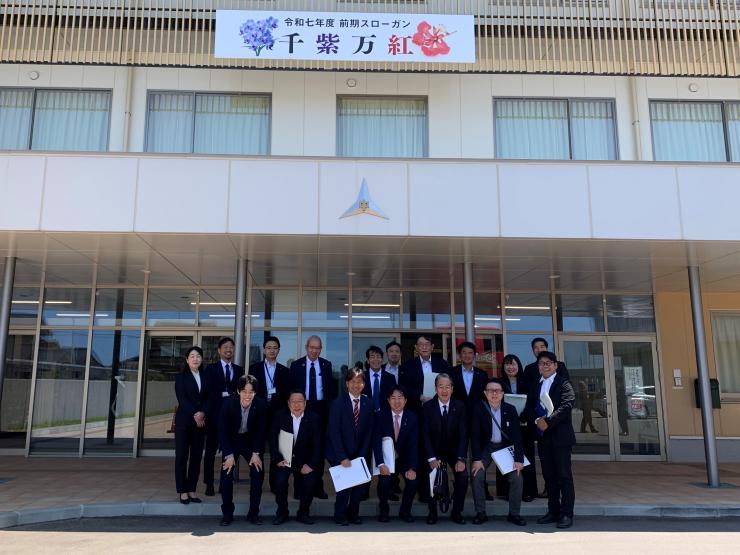
加賀市立東和中学校にて